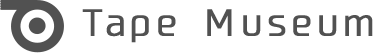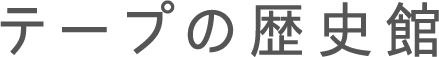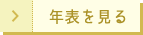第6章 合成高分子がもたらした転機 合成高分子との出会い
- TOP
- テープの歴史館
- 第6章 合成高分子がもたらした転機
- 合成高分子との出会い
合成高分子との出会い粘着テープの大きな転機
分子量がケタ違いに高い、高分子化合物
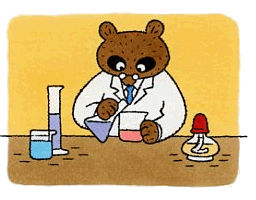
粘着テープは、今では数えきれないほどあります。それを可能にしたのが、第二次世界大戦後に台頭してきた「合成高分子」の技術です。
そもそも「高分子」とは何でしょう。
地球上の物質は、すべて分子から成り立っています。たとえば、コップ1杯の水には、水の分子(H2O)が無数に集まっています。
分子量は、重さの割合で示されます。酸素の重さを32(ミリでもグラムでもない、ただの32)とすると、水素は2、水は18、砂糖は342になります。この分子量がだいたい1万以上のものを「高分子化合物」といいます。たとえば、セロハンは5~6万、核酸(DNA)は400~800万。高分子化合物はケタ違いに分子量が高いのです。
粘着テープの素材となったものは、いずれも高分子
分子量が高いことから、高分子は実にさまざまな性質を持っています。低分子を砂にたとえるなら、高分子は粘土。カタチになりにくく崩れやすい砂に対して、粘土はカタチになりやすく、しかも優れた特性を発揮します。
絹や木綿などの繊維、天然ゴム、木材、紙、毛髪などは天然の高分子です。モノとモノをくっつけるために、昔から人々は布や紙にデンプンのりや、ニカワ、ゴムなどを塗ってきましたが、そのほとんどが天然高分子だったのです。高分子の特性を、上手に利用してきたと言えるでしょう。
高分子を人工的につくることで訪れた、粘着テープの大きな転機
20世紀になると、その高分子を私たちは人工的につくるようになりました。
1909年、ベークランドがフェノール樹脂を発明しました。これは熱加工すると成形品が硬くなるので熱硬化性樹脂といわれ、絶縁材料をはじめ優れた樹脂として広く使われるようになりました。
これをきっかけに合成高分子がさかんに研究されるようになり、ナイロン、ビニロン、ポリエステルといった合成繊維をはじめ、合成ゴム、合成紙などが登場します。必要な(または希望する)機能を持った素材を人間の手でつくることが可能になって、粘着テープも大きな転機を迎えます。