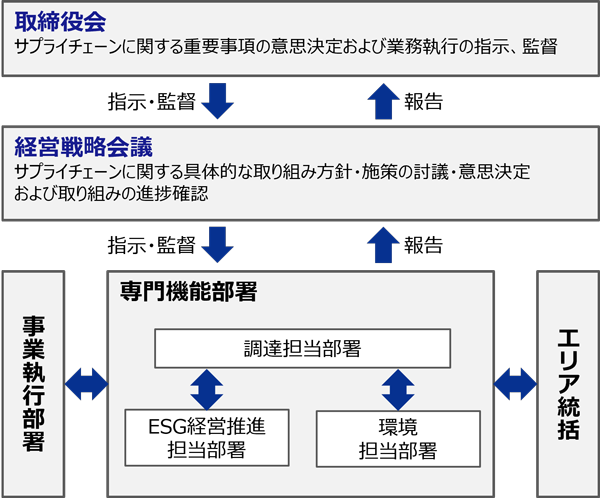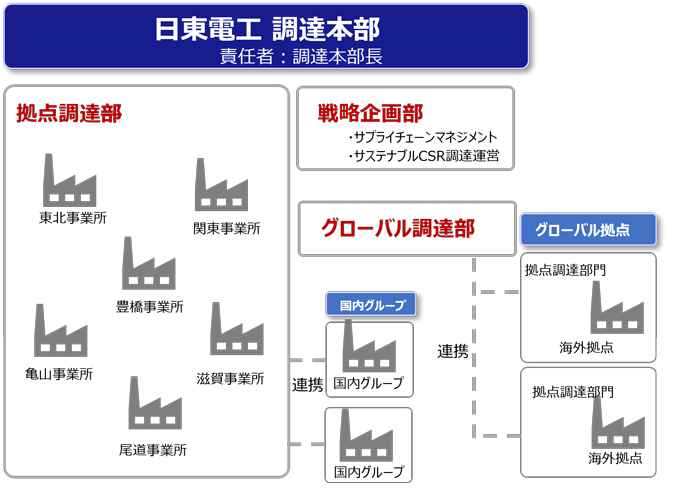職場環境や生産性の向上には、全ての働く人がディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を実現することが重要とされています。企業には就労形態を問わず、職場で働く全ての従業員において労働者の権利(人権)を尊重し、尊厳をもって接することが求められています。
1-1)強制労働の禁止
- 人身売買を伴う労働や監禁労働・奴隷労働などあらゆる形態の強制労働を禁止しなければなりません。
- すべての従業員を、雇用前に契約内容を合意した上で本人の自由意志をもって雇用しなければいけません。
- 契約内容の合意に使用する文書(雇用契約書や雇用条件通知書など)は、被雇用者が理解できる言語で作成しなければいけません。
- 雇用した従業員に対し、移動の自由に不合理な制限を設けてはいけません。
- 雇用した従業員は、正当な理由を説明して離職の希望を申し出た場合に、違約金なしに、いつでも自由に離職することを可能としなければなりません。
- 雇用した従業員からの手数料の徴収や不当な控除は禁止しなければなりません。
- 雇用した従業員の身分証の預託を義務付けることを禁止しなければなりません。
「強制労働」とは、自分の意志によるものでなく他のものに強要されることにより行う労働のことを言い、強制労働は深刻な人権侵害となります。
雇用条件や契約内容を本人が理解できる言語で説明することは、本人の就労の意志を確認するために必要です。また、手数料の徴収や不当な控除、身分証(パスポート、在留資格証、マイナンバーカード、年金手帳など)を会社で保管することを義務付けることなどは、離職の自由の制限につながる恐れがあるため、Nittoグループとして認めることはできません。
- ※ 手数料の徴収:採用時の紹介(斡旋)手数料など
- ※ 不当な控除:業務に必要な制服や個人保護具、研修の費用を個人に負担させることなど
1-2)児童労働の禁止
- 各国・地域における最低就業年齢に満たない児童を雇用してはいけません。
- 18歳未満の若年労働者を雇用する場合は、時間外労働や危険有害業務への就業、深夜勤務は禁止しなければなりません。
「児童労働」とは、各国・地域(または国際労働機関(ILO))で定めた最低就業年齢に満たない児童が従事する労働のことです。例えば日本では、労働基準法で義務教育終了まで(15歳に達した日以後、最初の3月31日を過ぎるまで)は、就業を禁止されています。また、基本的に18歳未満の危険有害業務への就業や深夜勤務は禁止されています。
- ※ 危険有害業務:有害物質を扱う作業や高所作業等
- ※ 深夜勤務:一般に午後10時から午前7時までの連続する少なくとも7時間を指す
就業年齢に関し、法令の定めがない国では、ILOの規定に準拠ください。また、もしも児童労働が判明した場合は、人道的立場からその児童の修学を支援するなど、救済することが求められます。
1-3)労働時間
- 時間外労働時間を含めた労働時間は、各国・地域の法令で定められた限度を超えてはいけません。
- 従業員には7日間に1日以上の休日を与えなければいけません。
- 各国・地域の法令に定められた年次有給休暇や長期休暇の権利を与えなければいけません。
- 勤務日数/時間、時間外労働時間を正確に記録しなければなりません。
著しい長時間労働は労働者の精神的・肉体的健康を害し、うつ病等の精神疾患や過労死・自殺などにつながる可能性があるため、「労働時間」を適切に管理しなければなりません。労働者の健康と安全を守るための労働時間の基準として、例えばサプライチェーンにおける労働環境の安全性や労働者の権利に対する支援を目的とした企業連盟であるResponsible Business Alliance(RBA)では、1週間の労働時間の上限を60時間と定めています。また、世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的とする国際機関である国際労働機関(ILO)では1週間の労働時間の上限を48時間と定めています。こうした国際的な基準を参考に自社の基準を設定いただくことを期待します。
なお強制労働を禁止する観点から、すべての時間外労働が自発的なものであることも求められます。
また、休憩や労働時間の決定は妊娠中や産後の間もなく復帰された方などジェンダーへ配慮することも望ましいです。
1-4)適正な賃金
- 従業員には、少なくとも各国・地域の法令で定められた最低賃金を支払わなければいけません。
- 超過勤務の手当は、各国・地域の法令に準拠して、正規の時給を割増した金額を支給しなければいけません。
- 従業員が理解できる言語で作成された給与明細を提示しなければいけません。
「最低賃金」とは、各国・地域の賃金関連法令で定められた最低の賃金を言います。同じく法律により従業員へ提供される福利厚生が定められている場合は、不足なくこれを提供する必要があります。
従業員に対する懲戒としての減給や不当な控除は、「働いた時間は給与を支払う」の原則に基づき禁止することが求められています。また、給与は労働時間に相当する額であるとともに、同一労働、同一資格には差別なく同一の賃金が支払われることも求められています。そのため、懲罰目的の賃金減額や不当な控除が行われていないことを期待します。
そして、従業員自身で業務に対する正しい報酬額が支払われていることが確認できるよう、言語や表現に配慮した給与明細の提示や内容説明が求められています。さらに、離職者に対しても、入社時に会社と合意した期間内に遅滞なく賃金が支払われることが求められています。
1-5)非人道的扱いや差別の禁止
- 虐待や各種ハラスメント行為を禁止するとともに、これらの事象に対応した懲戒方針・手続を明確に定義し、従業員に開示しなければいけません。
- 求人・雇用における差別がないようにし、職場における処遇の公平性確保に努めなければいけません。
- 宗教的慣習や障がいを有する方が就労に際し便宜を求めてきた場合は、合理的な配慮で対応しなければいけません。
従業員の人権を尊重し、精神的・肉体的虐待、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント等の各種ハラスメント、体罰・精神的もしくは肉体的な抑圧、言葉による虐待等の非人道的な扱いがないようにしてください。
「差別」とは、本人の能力・適性・成果などの合理的な要素以外により、採用、昇進、報酬、研修受講などの機会や処遇に差を設けることを言います。例えば、人種、民族、国籍、出身地域、皮膚の色、年齢、性別、性的指向、障がいの有無、宗教、政治的見解、妊娠、結婚歴、組合加入の有無、遺伝情報などに基づき、昇進や賃金に差をつけるようなことを言います。
雇入時健康診断の受診依頼は・健康診断、妊娠検査の結果が雇用条件としてみなされる可能性があるため、実施の目的(安全な労働環境を提供すること)を明確にして実施することが望ましいです。
また、従業員が本人あるいは周囲の方への非人道的扱いや差別に対する懸念を、安心して会社に伝えることができるような連絡プロセスを構築することが求められています。
1-6)従業員の団結権
- 労働環境・待遇の改善を実現する手段としての従業員の団結権や団体交渉権、平和的集会および結社の自由に対する権利を尊重しなければいけません。
「従業員の団結権の尊重」とは、各国・地域の法令に基づき、報復・脅迫・嫌がらせを受けることなく団体交渉等を行うために労働組合に加入する自由、団体交渉を行う自由等に配慮することです。